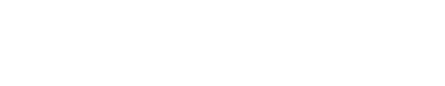「山形大学シードル2025」が完成!3月13日販売開始

本商品は、本学部附属やまがたフィールド科学センターエコ農業部門(高坂農場)で生産しているリンゴを原料にしており、醸造はHOCCA WINERY(奥羽自慢株式会社・山形県鶴岡市)、企画・販売は山形大学生活協同組合が行います。
今回のシードルでは、食用として定番の「ふじ」「紅玉」「王林」に加え、主に調理・加工用の「グラニース ミス」や、受粉樹に成る「ワルツ」「ポルカ」も活用しています。受粉樹はリンゴ栽培において結実を確保する ために植えられるもので、その果実は通常、生食には適しませんが、シードルに深みと奥行きのある味わいをも たらすため、今回も使用しました。栽培には高坂農場に出入りする農学部学生が関わり、リンゴの着色管理のための葉摘み・玉回しや、醸造前の洗 浄作業を山形大学生から構成される生協学生委員会OH,ONE!?(オーワン)部員が体験しました。
今年も約900本の販売が予定されており、完売した場合は11万円が「山形大学基金」等に寄附され、学生への支援として活用されます。山形大学生協店舗(小白川・飯田・米沢・鶴岡)のほか、同組合ホームページからも購入できます。
【山形大学生協HP】https://www.yamagata.u-coop.or.jp/


| « 農学部附属やまがたフィールド科学センター 技術専門職員 佐久間 拓也 » リンゴの栽培を担当しております、農学部技術職員の佐久間です。学生実習を担当させていただきましたが、皆さんとてもいい表情でリンゴを実際に見て、触って作業していました。また、収穫まであと2週間ほど、というタイミングでしたが、試食してもらったところ非常に好評で、良い体験になったことが伺えました。学生にとって良い取り組みであると感じています。 次に、農学部高坂農場のリンゴ生産の概要と今季の栽培についてお話しします。当農場では、40アールの面積で約100本のリンゴを10品種栽培しております。キズや色が悪いものはジュースやジャムに加工して販売していますが、それでも余剰が出た場合は廃棄となります。フードロス削減の観点からも、意義のある取り組みだと考えています。 今季の栽培についてですが、例年問題となっていた黒星病をほぼ抑えることができ、収穫まで元気な葉っぱの数が多く、最大限光合成を行うことができました。味は好評で、個人的にも今季のリンゴには満足しています。 前回、前々回と、本当においしいシードルをお届けできました。その味をさらに追求するため、ただ甘い、酸っぱい、ではなく、奥深いシードルになるよう、リンゴの品種や割合を工夫しています。ぜひ、皆様に当農場を知っていただき、一緒に今季のシードルを楽んでいただければと思っております。 |
|
≪ 奥羽自慢株式会社 製造部 石塚 雅英 » 2023年から手がけているシードルですが、おかげさまで今回で3年目を迎えることができました。今年も発売できることを、大変嬉しく思います。毎年試行錯誤を重ねながら、味わいの向上に努めてまいりました。本年は、受粉樹が2種類結実したということで、山形大学の佐久間様と相談し全量収穫してもらうことにしました。収穫時は受粉樹をどのような配合で加えるかは決めていませんでした。通常受粉樹は生食用ではあまり使用しない品種となりますが、それぞれのりんごの味わいや収穫量のバランスを見ながら配合を考えました。その結果受粉樹を全量使ってみても面白いのではないかという考えに至り使用することを決断しました。 今年度は計6種類のリンゴを使用しています。その結果、受粉樹由来のタンニン(渋味)や酸味が強調され昨年よりも味わいに一層の膨らみと奥行きが生まれたと感じています。また、青リンゴの割合を増やしたことで、爽やかな香りが際立つ仕上がりとなりました。 また当社のシードルは瓶内二次発酵という技法を採用しております。これは酵母が糖分を分解する際に発生させる二酸化炭素を、適切なタイミングで加熱殺菌することにより酵母を不活性化させ、残糖やガス圧をコントロールする技法となります。スパークリングワインの製法の中では特に手間のかかる技法となりますが、これにより人工的にガスを加えるのでは得られない、自然で優しい泡立ちを楽しむことが出来るシードルに仕上げています。贅沢に6種類のリンゴを使用することで、作り手としても新たな発見が多く、非常に楽しい挑戦となりました。そして出来上がったシードルは、私たち全員が納得できるものに仕上がったと自負しています。 近年、アルコール離れが進んでいますが、シードルは低アルコールでありながら、リンゴ酸、カリウム、ポリフェノール、ビタミンなど、身体に嬉しい栄養素を豊富に含んでいます。このシードルを通じて、お酒に馴染みのない方や興味を持ち始めた方はもちろん、普段からお酒を楽しまれている方にも、シードルの魅力を知っていただくきっかけになれば幸いです。また、この取り組みを通じて、山形大学様の活動をより多くの方に知っていただく機会となることを願っております。 |
■掲載日:2025.03.12