食品・応用生命科学コース
本コースは、食品栄養化学、分子細胞生化学、動物機能調節学、発酵制御学、応用微生物学、バイオマス資源学、食品創製科学の7分野から成り、高等動物や植物、微生物など多様な生物を教育研究の対象とし、広範囲の領域を基礎から応用まで学ぶことができます。ここで共通するキーワードは「生物の生理機能の解明」です。食品健康、環境修復、発生、タンパク質工学、物質生産に絡んで生じる生物・生命現象の仕組みを明らかにしていくことが課題です。
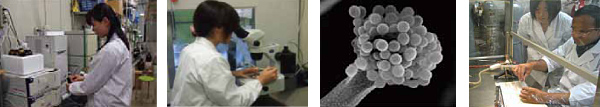
| 特色ある授業 | 主な授業 | |
|---|---|---|
| 1年次 | 食品・応用生命科学概論 食品・応用生命科学全般についての概要、ならびにその中の食品栄養化学、分子細胞生化学、動物機能調節学、発酵制御学、応用微生物学、バイオマス資源学のそれぞれの概要を紹介します。 |
食料生命環境学入門 現場から学ぶ農学 基礎農学セミナー |
| 2年次 | 食品微生物学 食生活との関連から微生物をとらえ、応用微生物学的見地から、麹菌等の醸造微生物の特性や物質生産、また、従来の食品微生物学的見地からの食品の保蔵・管理について学習します。 |
バイオマス資源学 細胞生化学 生命バイオ分析化学 分子栄養学 |
| 3年次 | 動物発生工学 |
微生物機能開発学 |
| 4年次 | 研究プレゼンテーション演習 研究成果の報告について説得力のあるプレゼンテーションの仕方を習得します。 |
公衆衛生学 |
教育研究分野紹介
食品栄養化学分野
食品が持つ生理機能と食を通じた健康科学について教育研究を行っています。具体的には、肥満・脂質異常症・糖尿病・高血圧・動脈硬化症などの生活習慣病の予防・改善に有効な食品由来の機能性成分について、培養細胞や実験動物を用いて研究を行っています。
分子細胞生化学分野
主に高等植物をターゲットとして、生命及びその活動の仕組みを生化学・分子生物学的に理解・解明することを通して教育研究を行っています。
動物機能調節学分野
主に実験動物や家畜・家禽類の生殖生理学と発生工学について教育研究を行い、産業動物の生産や生殖補助医療の分野などへ応用可能な技術開発を目指しています。
発酵制御学分野
糸状菌発酵プロセスによる有用物質(酵素や生理活性物質)生産とその構造機能相関について教育研究を行い、関連産業への応用を目指しています。
応用微生物学分野
各種環境中における微生物の多様性や生理生態学的特性の解明、さらには微生物を利用した廃棄物の再資源化や環境浄化等への応用について教育研究を行っています。
バイオマス資源学分野
農産・食品系副産物を主体とした未利用バイオマスの再資源化とその循環利用に関する教育研究を行っています。具体的には、再生可能資源であるバイオマスからの有用物質およびエネルギー回収・生産を促進する新規リファイナリー技術の開発や微生物機能を利用したバイオマス変換技術の開発に取り組んでいます。
食品創製科学分野
食材や未利用・低利用資源から新規食品開発につなげるための食品加工・製造・分析技術などの技術開発や応用研究について教育研究を行っています。食品の特性解明や地域に根付いた食品開発にも取り組んでいます。
教員紹介
| 職名 | 氏 名 | 教育研究分野 | 専門的内容 |
|---|---|---|---|
| 教 授 | 加来 伸夫 | 応用微生物学 | 嫌気性微生物の生理・生態学および微生物を用いた環境浄化 |
| 教 授 | 木村 直子 | 動物機能調節学 | 哺乳類卵母細胞の減数分裂機構,家禽類の生命工学技術の開発 |
| 教 授 | 小関 卓也 | 発酵制御学 | 糸状菌の産生する有用酵素の探索および酵素工学的研究 |
| 教 授 | 塩野 義人 | 発酵制御学 | 微生物や植物により生産される生理活性物質に関する研究 |
| 教 授 | 豊増 知伸 | 分子細胞生化学 | テルペン類の生合成に関する分子生物学的研究 ~受験生の皆さんへ~ |
| 教 授 | 三橋 渉 | 分子細胞生化学 | 高等植物の発生・分化・成長の生化学的・分子生物学的研究 ~受験生の皆さんへ~ |
| 教 授 | 永井 毅 | 食品創製科学 | 食材や未・低利用資源由来の食品加工・製造・分析技術開発ならびに地域食品開発 ~受験生の皆さんへ~ |
| 准教授 | 渡辺 昌規 | バイオマス資源学 | 農産・食品系廃棄物からのエネルギー、有価資源回収および新規リファイナリー技術の開発 |
| 准教授 | 井上 奈穂 | 食品栄養化学分野 | 食品由来機能性成分による生活習慣病の予防・改善に関する研究 ~受験生の皆さんへ~ |


